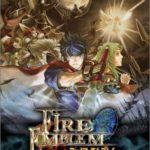Twitter にて、「いいねされた数だけハマったゲームを紹介する」というハッシュタグ企画を取り上げたところ、思った以上の反響をいただいたので、紹介した内容をまとめておきます。
数が多いので記事を二分割、本稿は、その後編となります。前編はこちら。
前編が90年代~00年代、SFC, PS, PS2, GBA のタイトルが中心だった一方、後編はややマニアックなタイトルや、比較的最近のスマホゲーム、アナログゲーム(ボードゲーム)等も取り扱っています。
Twitter での投稿内容をそのままコピーしてまとめておりますので、文字数制限の関係で情報が圧縮されている点や、口調にブレがある点などについては、ご承知おきいただければと思います。
16.ワイルドカード(2001年 WSC)
みんな大好きサガシリーズ枠。
TRPGのようにキャラのスキルを駆使して障害を乗り越える、アンサガの原型とも言える作品です。
アンサガが元々携帯機向けの企画として動いていた、という話も、元はワイルドカードの関連作だったのかな、なんて考えてしまいますね。
パラメータの意味がわからない、いきなり主人公が交代して詰みそうになる、など説明不足による初見殺しの連続は、まさにサガシリーズという感じ。
しかし全てをカードで表現したシンプルなビジュアルは、ゲームプレイに集中させてくれて、高難度でも何度もプレイしてしまう中毒性があります。
17.逆転裁判3(2004年 GBA)
シリーズで一番好きなのが3なのですが(ゴドー検事すき)、123は1セットですよね。
GBAのゲームにして、とにかく演出のセンスがすごくて、バシン!ドガァン!バァン!といった SE が多用され、ボイスが無くてもキャラの会話がすごく生き生きとしています。
ゲームの演出論みたいな話で、自分がよく引き合いに出すシリーズでもあります。
逆転裁判、ゲーム性は特別面白いものでもないのですが、裁判パートでテキストを読み進めるボタンを押す気持ちが、どんどん高揚してナルホドくんにシンクロしていく。これはまさに、ゲームならではの演出だと思います。
逆転裁判はゲームの演出としても優れている一方で、今考えてみると VOICEROID 動画の参考としても、すごく良い資料なのではないかな、と感じます。SE バンバン使うのも、もはや定番手法の一つになっていますからね。
18.テラバトル(2014年 iOS/Android)
タッチで2Dの駒を動かすだけという、無駄を削ぎ落したシンプルな操作性でありながら、1手1手考える要素がとても面白い。
坂口博信氏のゲームといえば、映画的演出という印象も強いですが、本作はスマホという舞台にとても上手く最適化された作品だと思います。
システムがパズドラの影響を受けているのは、制作者も語っている通りなのですが、パズドラがあくまで『パズル』であるのに対して、テラバトルは敵との距離や陣形などを意識した『戦術シミュ』に近い内容になっています。
シミュレーション好きな坂口氏らしさが混ざった結果なのかも知れないですね。
19.ウィザードリィ リルガミンサーガ(1998年 PS)
1~3のリメイクのパックです。
1の原作は1981年で、日本におけるRPG黎明期に大きな影響を与えた作品です。特に初代FFなどは、強い影響を受けているのが見て取れます。
聞いたことはあるけれど、遊んだことは無い、という人も多いのではないでしょうか。
キャラメイクをし、酒場でパーティを組み、ダンジョンを探索し、宝箱からアイテムを手に入れ、無事に街へ帰ってきて、宿屋で休んだら、またさらに奥へ…。
RPGにおける最低限の『冒険』のエッセンスが詰まったウィザードリィは、今遊んでも楽しめる作品です。電源系RPGの起源に興味のある方は是非。
RPG を構成する要素の中で、どれが 必要/不要 とは言えないと思いますが、個人的に最も重要視している要素の一つとして「パーティが協力して、強敵に立ち向かう」というのがあります(だからFF5とかFEが好き)。
Wiz を初めて知ったとき、まさにこの要素が凝縮されていて、とてもワクワクしました。
20.カービィのエアライド(2003年 GC)
Aボタンとスティックだけで、カービィのレースゲームは成り立つ。
斬新な発想でありながら誰にでも取っつきやすく、しかし何度も繰り返し遊べて奥が深い。カービィシリーズやスマブラを生み出した、桜井イズムの詰まった1作だと思います。
シティトライアルの面白さについては多くの人が言及している通りなのですが、個人的なお気に入りはウエライド。
真上から見下ろし、スクロールも無く1画面に収まったコースで、アイテム有りステージギミック有りのハチャメチャレース。
一層わかりやすいゲーム性で、パーティゲームとして最適です。
21.けいおん!放課後ライブ!!(2010年 PSP)
遥か古の時代、「キャラゲーに当たり無し」とはよく言われていたものですが、本作は深夜アニメの派生作品にして、当時としては異例の20万本を売り上げたタイトルです。
収録楽曲はアニメ1期の内容で、キャラソンまで幅広く遊ぶことが出来ます。
収録数は20曲程度なのですが、バンドメンバーのパートごとに異なる譜面を遊べる(要するにバンブラ形式)ため、譜面の数は実質5倍。
ファンアイテムとしても、非常に出来の良い作品でした。
アニメ2期の内容も含めた続編を期待していたのですが、後のアーケード方面の展開はイマイチだったようで…。
22.メルクストーリア(2014年 iOS/Android)
携帯電話でのゲームが、ポチポチゲーから本格的なゲームに移り変わっていた時代。
「放置して進めるゲーム性」というのは、まさに携帯電話に合った上手いアイデアだなぁと思いました。
(起源の話になると『にゃんこ大戦争』とかの方が先ですが)
また、メインストーリーはそんなでもないのですが、イベントの短編シナリオの出来が滅茶苦茶良いです。
その場限りの舞台とキャラでありながら、しっかりとキャラの心情や葛藤、障害を描き、最後は余韻を残した終わりになる…。
どれもこれも泣けてしまう内容で、短編の参考にとても良いゲームです。
初期のイベントしかわからないので、後のイベントはそんなでも無いのかも知れません。
(初期はライターさん1人が書いており、途中から複数人体制になったとかなんとか)
23.零~紅い蝶~(2003年 PS2)
幽霊をテーマとした、静かな恐怖を感じる和風ホラーシリーズ。
主人公が戦闘能力を持たない、か弱い女の子であることに、ゲームデザインとしての意図を持たせているのが上手いなぁと感じます。
まさに日本人にしか作れないゲームだと思うので、世界的に名を広めて欲しい。
当時としては非常に希少な、姉妹同士の百合を扱った作品でもあります。
特徴的なのはエンディングで、PS2原作版で収録されている2つのエンディングは、どちらも暗い結末を迎えます。
Xbox版でハッピーエンドが追加されたと思えば、Wiiのリメイク版ではなぜかさらにドぎついエンドが2つ…。衝撃的です。
凍蝶エンド、ほんとどんな気持ちで作ったんだろう。同人的なゲームならまだしも、大企業の出すゲームとしては、あまりに尖っている。しかもリメイク版の追加要素で。零らしいといえば零らしいけれど。すごい。
24.世界の七不思議(2011年 アナログ)
同時期に流行り始めた、ドミニオンやアグリコラと比べると少しマニアックかも知れませんが、それなりに有名なはず。
建造物を建築していって最終スコアを競うという、各人のソリティア的になりがちなタイプですが、隣同士のプレイヤーとの駆け引きがあって面白い。
タイトルになっている通り、七不思議それぞれの文明をプレイヤーが担当出来るのですが、他にもスコアにつながる技術や文化が七色に分けられていたり、何かと7という数字に合わせてデザインされているのが美しい。
ただ、7人プレイはプレイヤー同士の干渉が薄くなるので、4人か5人ぐらいが面白いです。
25.Fist of Dragonstones(2002年 アナログ)
恐らく日本語化されていない?ので、知名度は低いと思います。
ファンタジーの世界観で競りゲー、というフレーバーがなかなかに素敵。
ウィッチやフェアリー、ドラゴンといった役職カードの競りを行っていき、規定の勝利点を集めたプレイヤーの勝ちです。
ラウンドごとに復活するお金と、1回限り使い捨てのお金の区別があり、ブーストをかけるタイミングの駆け引きがあったり、競りを無効化する能力を持つウィッチの存在など、読み合いが面白い。
価値感覚がわからなくても、全突っ張したりコツコツ集めたり、ぐらいの雑な感覚でも楽しめるのが良いです。
26.DiXiT(2008年 アナログ)
カードゲームと言えばカードゲームなのですが、重要なのはイラストだけ。
親プレイヤーがテーマを決め、全員がテーマに沿ったイラストカードを非公開で出して、それらをシャッフルし、親のカードを当てるゲーム。
親は「全員が当たりもせず、外れもしない」状態を目指す。
アナログゲームといえば、数字のバランスなどが緻密に作り込まれたゲームも多いのですが、このゲームは「言葉に合わせてイラストカードを出す」だけの、誰にでもわかるシンプルな内容。
でありながら、決して大味なゲームではなく、それでいて盛り上がれる、とても美しいゲームデザインだと思います。
27.犯人は踊る(2014年 アナログ)
大学院を出て以来、アナログゲームを遊ぶ機会はどうしても減っていたのですが、最近遊んだ中ではダントツで面白かったゲーム。
犯人当て、という意味では人狼系のゲームなのですが、手札の犯人カードはババ抜きのように、どんどん他プレイヤーに移っていくのが特徴。
人狼のようにじっくり考えるというより、どんどん混乱して盛り上がるタイプです。
1プレイは短くサクサク進むので、つい何度も再戦してしまいます。
入れ替わる手札が現在の秘密の役職となる、という意味では、人狼というよりもラブレターの拡張的な印象も受けるゲームですね。
あとがたり的な
放っておくと本当に、SFC/PS 世代で全部埋めてしまうのですが、そんな化石みたいなムーブ、ゲーム開発者としてどうなのという自問もあったので、スマホのゲームとか最近のアナログゲームとか、半ば無理矢理ひねりだしていました。
ただ、最新ハードのタイトルとか、有名過ぎて偉大過ぎるゲーム(具体的に言うとクロノトリガー)とかは、自分が紹介するのもなぁ、という気持ちもあったので、その辺りはちょっと除けていたところもあります。
あと、当時はそこまでハマっていなかったけれど、最近動画でハマったタイトルも、なんか動画勢っぽいムーブになってしまいそうだったので、意図的に避けました。(具体的に言うとサガフロンティア2)(語りたいことは山ほどある)(語り切れない)